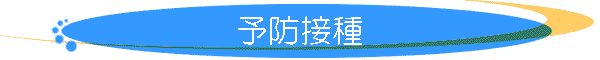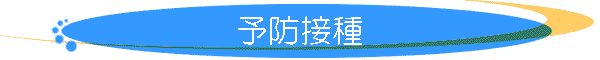1995(平成7)年の予防接種法の改正で個別接種が原則となりました。ただし、市町村でそれぞれ予防接種の要領が異なります。各地区の予防接種の要領をご覧ください。接種前にワクチンについて小冊子予防接種と子どもの健康
2008年3月改訂版(予防接種リサーチセンター)をお読みいただき、予防接種についてご理解いただくようになっています。ご心配なことや分からないことがあれば
かかりつけ小児科で十分に説明を受けられてください。小児科医はご理解いただけるように説明する
はずです。
その後、BCG接種に関わる結核予防法の廃止や予防接種法の一部改正が行われましたので変更された点があります。また、福岡県内であれば相互乗り入れの取り決めがおこなわれ、ほとんどの市町村でポリオ、BCG以外の定期接種はどこでも無料で受けられるようになっています。詳しくはかかりつけ小児科医におたずねください。
予防接種の当日は、母子手帳のご持参もお忘れなく。
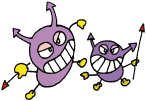
予防接種対策に関する情報 (厚労省)
予防接種のページ
(国立感染症研究所 感染症情報センター)
予防接種ガイドライン
2008年3月改訂版 (予防接種リサーチセンター)
予防接種スケジュール (予防接種リサーチセンター)
Know
VPD! - ワクチンで防げる病気(VPD)を知って子供たちの命を守る
(
「VPDを知って、子どもを守ろう。」の会 )
おすすめ予防接種スケジュール おすすめ予防接種スケジュール(ロタワクチン含む)
ワクチン製剤については
細菌製剤協会HP
をご覧ください。
北九州市の場合を説明 します。
定期接種(予防接種法に基づくワクチン:勧奨接種)として
◎ 三種混合ワクチンDPT
(ジフテリア:百日咳:破傷風) :不活化ワクチン(皮下注射)
1期は生後3〜90ヶ月までに初回として3〜8週間あけて3回接種。その後6ヶ月以上あけて追加接種します。乳児期の百日咳感染を予防するため、生後3〜12ヶ月までに3回接種し、3回目接種後12〜18ヶ月の間に追加接種をします。
百日咳の既往が明らかな場合でもDPTを接種できるようになりました。
副反応として注射部位の発赤、腫脹、しこり(硬結)がみられますが一過性です。
◎ ポリオ :不活化ワクチン(皮下注射)
生後3〜90ヶ月までに初回として3〜8週間あけて3回接種。その後6ヶ月以上あけて追加接種します。
副反応として注射部位の発赤、腫脹、発熱がみられますが一過性です。
◎ DPT+不活性化ポリオの4種混合ワクチン
生後3〜90ヶ月までに初回として3〜8週間あけて3回接種。その後6ヶ月以上あけて追加接種します。
副反応として注射部位の発赤、腫脹、しこり(硬結)、
発熱がみられますが一過性です。
◎ BCG :生ワクチン(スタンプ方式)
2005(平成17)年4月からツベルクリン反応が廃止され、直接BCG接種となり、従来の3か月 〜4歳未満より出生時〜6ヶ月未満での接種に変更されました。
2007(平成19年)4月の結核予防法の廃止に伴い、BCGは予防接種法にもとづく接種に変更 されました。理想は3ヶ月〜6ヶ月未満。北九州市では2008(平成20)年4月より個別接種になり医療機関で受けることになりました。
副反応として、まれに接種した側の腋の下にあるリンパ節(腋窩リンパ節)が腫れることがありますが通常は自然に消失します。心配な場合は医療機関に御相談ください。
◎ 二種混合ワクチンDT(ジフテリア:破傷風) :不活化ワクチン(皮下注射)
2期は小学校6年でDTを1回接種します。
◎ 麻しん風しん混合ワクチン
(MRワクチン) {麻しんワクチン・風しんワクチン
}
2006(平成18)年6月より麻しんワクチンと風しんワクチンは混合ワクチン(MRワクチン)が導入され2回接種となりました。1期が生後12〜24ヶ月未満(2歳の誕生日の前日まで)。2期の接種時期は5才〜7才未満で小学校就学日の1年前から就学日前日までの間です。副反応として接種後7〜10日頃に発熱や軽い発疹が約10〜20%にみられます。麻しんと風しんの単独ワクチンも上記の1期、2期の期間であれば定期接種として接種できますが、有効性や副反応に差がないことよりMRワクチンをお勧めします。
2008年4月1日から5年間の期限付きで、
第3期(中学1年生相当世代)、第4期(高校3年生相当世代)に拡大されています。対象にあたる方々は、忘れずに接種を受けましょう。
◎ 日本脳炎ワクチン :不活化ワクチン(皮下注射)
1期は生後6〜90ヶ月で初回は1〜4週間あけて2回接種します。1年後に追加1回。理想は初回が3才、追加が4才です。その後9〜13才未満に2期を接種します。
任意接種として
◎ Hibワクチン(インフルエンザ菌b型) :不活化ワクチン(皮下注射)
インフルエンザ菌b型(冬〜春に流行するインフルエンザウイルスとは異なります)による重症感染症(敗血症・髄膜炎や急性喉頭蓋炎)を予防するワクチンで世界中の多くの国ですでに使用され、その有効性は実証されています。
平成23年1月から公費負担です。
◎ 小児用肺炎球菌ワクチン :不活化ワクチン(皮下注射)
平成23年1月から公費負担です。
◎ 水痘ワクチン(みずぼうそう):生ワクチン(皮下注射)
有料
1才以降に1回。副反応はほとんどありません。ワクチンを接種しても10〜20%は自然感染しますが比較的軽く済むようです。
◎ おたふくかぜワクチン :生ワクチン(皮下注射) 有料
1才以降に1回。2〜3%に接種後2〜3週に耳下腺が軽く腫れたり熱がでることがあります。また数千接種に1例無菌性髄膜炎を合併することがありますが自然感染での頻度に比べてはるかに少なくまた後遺症もほとんどありません。
自然感染による難聴が500〜1000人に1人の頻度で合併します。これを予防するためにもワクチン接種をお勧めします(ワクチンの副作用による難聴の報告はありません)。
◎ インフルエンザワクチン :不活化ワクチン(皮下注射) 有料
生後6ヶ月以上の全年齢が対象で1〜4週(理想的には3〜4週)あけて2回接種します。13才以上では1回接種でも抗体上昇が期待できますので通常は1回のみです。
乳幼児・学童では細かく接種量が設定(1才未満0.1ml、1〜5才0.2ml、6〜12才0.3ml)されています。副反応は局所の発赤、かゆみが見られる程度で、発熱などの全身症状は
まれです。卵アレルギーのある場合はかかりつけ小児科医に相談してください。
◎ 子宮頸がん予防ワクチン :不活化ワクチン(皮下注射)
平成23年1月から公費負担です。
つぎの予防接種までの間隔